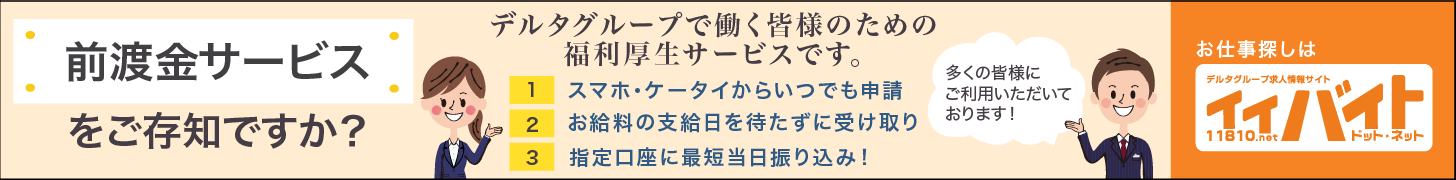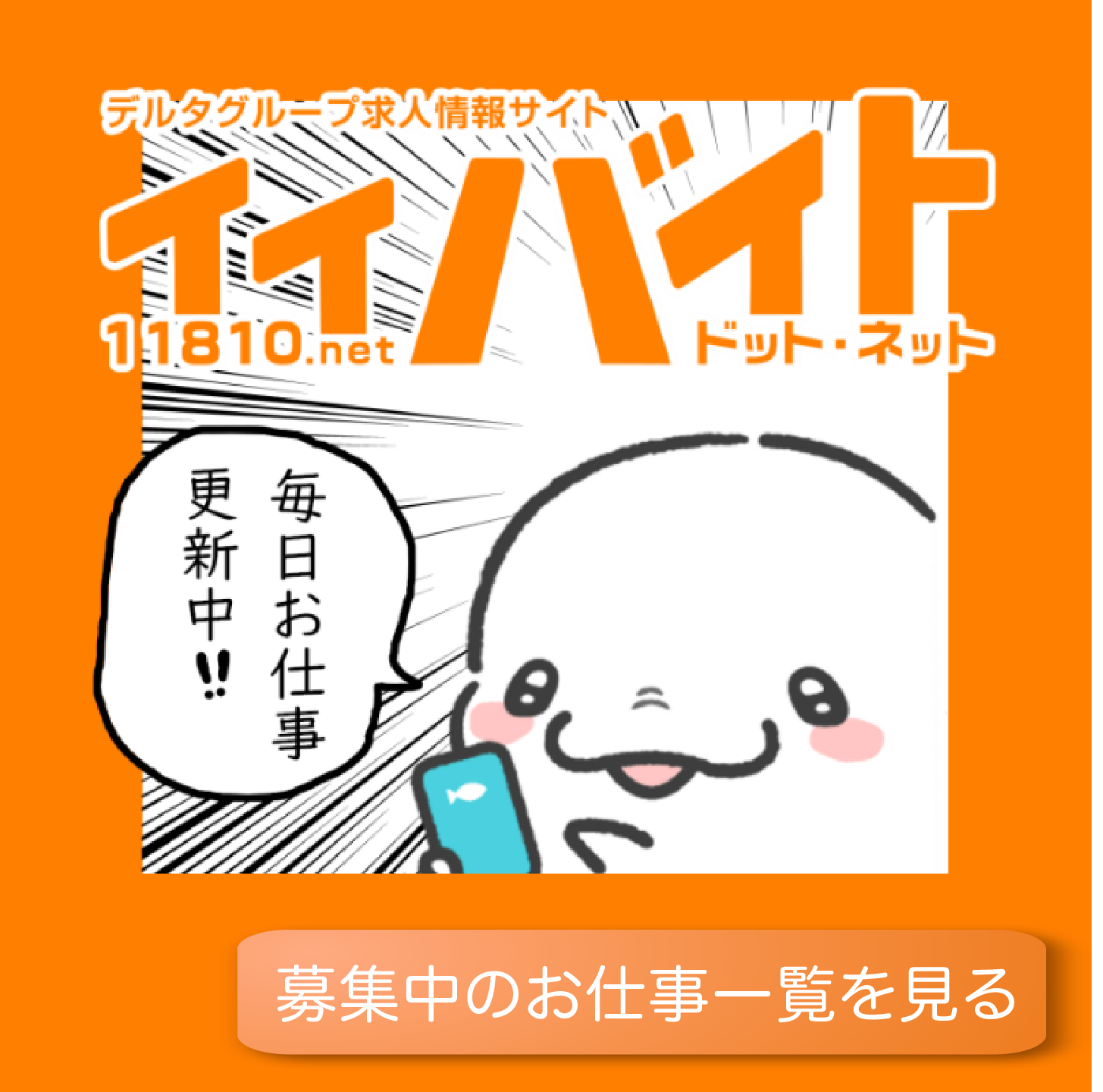実際に会社を退職した経験がある人であればわかると思いますが、退職には上司からの引き止めや後任者への引き継ぎ等、面倒な事柄がつきまとうものです。
退職をスムーズに進めて新たなスタートを気持ちよく切るには、上司に退職や転職の旨を伝える前にしっかりと準備を整えておく必要があります。
今回は、会社に退職や転職の意思を伝える前に準備しておきたいことに加え、退職届や引き継ぎに関するあれこれを解説します。
退職前に確認しておきたい3つのこと
上司に退職や転職の意思表示をする前に、次にあげる3つの事柄を確認しておくとその後の退職に向けての活動がスムーズに進みます。
- 辞めるという確固たる決意をする。
- 辞めるタイミングで転職先も探し始める
- 引き継ぎ等できる様に業務の整理を始める
辞めるという確固たる決意をする
上司に退職の意思を伝える際に付きものなのが引き止めです。
退職希望者が優秀な社員であればあるほど、その人材を失うことは会社にとって大きな損失につながるため、「君はわが社にとって必要な人材なんだ」等と諭して引き止めようとします。
当然に単純な人手不足でもこの手の引き留めはよく発生する為、現代において退職時の引き留めはよく見る光景です。
この引き止めを上手くかわして会社に退職を受け入れてもらうには、辞めることへの確固たる決意が必要です。
退職の意思を上司に伝える前に、「自分はなぜ退職したいのか」「退職後どのようなビジョンを描いているのか」を自問自答し、退職の決意をどんな引き止めにも揺るがない確かなものにしましょう。
本当に素晴らしい職場ならあなたの転職を応援してくれるはずです。
辞めるタイミングで転職先も探し始める
退職する気持ちが固まったら、退職の準備を進めると同時に新しい勤務先を探し始めましょう。
退職してから転職先を探そうとすると、「早く決めなくちゃ」という焦りから会社選びに失敗したり、なかなか転職先が決まらず職歴にブランクが生まれてしまう可能性があります。
理想を言えば、退職が決まる前に転職先を決めてしまうと良いでしょう。
新しい勤務先が決まっていれば、金銭的な不安を感じずに退職の準備が進められますし、上司から引き止められても「転職先が決まっているから」とかわしやすくなったりするからです。
退職前に転職先が決まらなくても、「退職活動と転職活動はワンセットである」と心得ておきましょう。
また、失業給付金を受け取ることはできるのか、自己都合退職であっても給付制限の対象にならないかなどハローワークでの確認もしておくと退職時次の仕事が見つかっていなくてもある程度安心できるかもしれません。
引き継ぎ等できる様に業務の整理を始める
退職に不可欠なのが後任者への引き継ぎです。
退職を伝える前に引き継ぎに関わる業務の整理をしておくと、後々上司と引き継ぐ業務の内容や引き継ぎ完了までの期限を調整する際に話がスムーズに進みます。
具体的には業務の内容や取引先をリストアップしたり、業務をスムーズに進めるためのマニュアルを作成しておくと良いでしょう。
なお、引き継ぎの準備をしていることを同僚や上司に悟られると、職場に無用な動揺や憶測を招く恐れがあるため、退職の意思表示前の引き継ぎ準備は個人でできる範囲に留めておくのが賢明です。
準備ができたら退職の意思表示をしよう

上司に退職や転職の意思を伝えるときは、相談ではなく確定事項として伝えるのがポイントです。
相談として退職の意思表示をしてしまうと、執拗な引き止めに遭う可能性が高まるからです。
退職の意思表示は退職を希望する日の1カ月前までに行うと良いでしょう。
民法では、退職希望日の2週間前までに退職を申し出れば問題ないとされています。
しかし、退職希望日から2週間前の申し出だと、業務の引き継ぎや人員の補充を急ピッチで行わなければならないため、会社側に大きな負担がかかります。
その結果、

等と引き止められる可能性が高くなります。
このような事態を防ぐには、退職希望日から1カ月程度の余裕を持って退職の意思を伝えるのが好ましいと言えます。
なお、就業規則に退職願や退職届を提出するタイミングに関するルールが設けられている場合には基本的にはそれに従う方が望ましいです。
しかし、今あなたがパワハラやセクハラなど違法な労働環境で働いており、今すぐにでも職場を抜け出した方がいいと判断される状態であれば例外として即時退職する為に動くことをお勧めします。
退職の旨を伝えるときには直属の上司に口頭で伝えます。
口頭に加えて退職願も合わせて提出すると、言った言わないで生じるトラブルを回避できるでしょう。
退職の意思表示をしたら、上司と相談して詳細な退職日を決定します。
このとき、何かと理由をつけて退職日を先延ばしされることもあるでしょう。
そんなときは心に決めた退職の決意を思い出し、しっかりと自分の希望を伝えることが大切です。
具体的な退職日が決まったら、次は退職届を作成して提出します。
退職届も退職日の2週間前までに提出すれば問題ありませんが、退職日の1カ月前までに提出するのが一般的です。
退職届を書く際のポイントは次の4点です。
- 書き出しには「私儀」(わたくしぎ)と書く。
- 文中には「○○年○月○日をもって退職します」と上司と相談して決めた退職日を書く。
- 退職日とは別に退職届を提出する日付も記載する。
- 宛名は実際に提出するのが上司であっても社長の名前を書く。
これらのポイントを踏まえた上で退職届を書き、直属の上司に提出しましょう。
引き継ぎと退職後にすること

退職や転職の意思表示を行った後に待っているのが引き継ぎです。
引き継ぎとは、後任者に仕事の進め方や進捗状況、取引先やその担当者の情報等を伝えることです。
引き継ぎをしっかり行わないと、仕事がスムーズに回らなくなって職場に迷惑をかけたり、今まで退職希望者の築いてきたノウハウが継承されずに無駄になったりと、企業にとってさまざまな不利益が生じます。
これらを防ぐためにも、上司との十分な相談の上で漏れのない引き継ぎをしましょう。
引き継ぎは
- 引き継ぐ事柄の整理
- 上司との引き継ぎ事項のすり合わせ
- マニュアルの作成
- 後任者への説明
- 社外の方への挨拶回り
というような流れで行われます。
社外への挨拶回りを行う際は、退職する旨やこれまでの感謝を伝えるとともに、後任者の紹介も行うと良いでしょう。
引き継ぎを終え、いよいよ退職となったときにもやらなければならないことがあります。
それは退職後の処理です。
具体的には会社から預かっていたものを返却したり、逆に会社からもらっておく必要があるものを受け取ったりするのが退職後の処理に当たります。
返却するものとは健康保険被保険者証や社員証、それから名刺等会社から支給されていたもの全般です。
反対に、会社から受け取っておく必要があるものには雇用保険被保険者証、源泉徴収票、離職票等があります。
雇用保険被保険者証と源泉徴収票は転職先に提出する必要がある書類であり、離職票はハローワークに失業手当を申請する際に必要な書類です。
失業手当とは、職を失った人の生活を安定させると同時に再就職への支援として給付されるお金のことです。
失業手当を受け取るには「現在失業中であること」「退職までの2年間で雇用保険への加入期間が通算12カ月以上あること」「ハローワークに求職申し込みをしていること」の3つの条件を満たす必要があります。
やむを得ない理由で転職先を決めずに退職した方は、この失業手当を申請して転職活動中の金銭的負担を和らげると良いでしょう。
退職の意思表示が難航したら退職代行サービスを使おう

これまで退職や転職の意思を伝える前に準備しておきたいことや意思表示をした後に行う退職への活動をいくつか紹介してきました。
しかし、転職活動や引き継ぎの準備を着々と進めているのに勇気が持てず、「退職したい」と上司に伝えられなかったり、退職への確固たる決意をしたにもかかわらず、上司からの説得にほだされて結局退職できなかったりする人もいるでしょう。
このような状態に陥っている人に知ってほしいのが、退職代行サービスの存在です。
退職代行サービスとは、退職を希望する労働者に代わって弁護士や代行業者が会社に退職の意思を伝え、退職に関する事務処理を行ってくれるサービスのことです。
退職代行サービスを活用すれば、上司と直接交渉せずに会社を辞めることができますから、執拗な引き止めや嫌がらせに遭うことなく退職できます。
また、退職代行サービスは「退職したことを両親に伝えないでほしい」や「離職票を郵送してほしい」等、退職の意向以外の要望も会社側に伝えてくれますので、退職希望者の望む形での退職が実現しやすくなります。
退職代行は、退職希望者からの相談を受けて「どのように退職したいか」等の希望を聞き取ることから始まります。
そして、退職希望者からの入金確認後、退職代行業者が会社と連絡を取り、退職希望者に代わって退職の意思表示や事務処理を行います。
サービスによっては代行業務が完了し、退職できてから料金を支払う場合もあります。
しっかり準備すれば退職はうまくいく!
転職活動と同様に、会社を辞めるときにもさまざまなステップを順番にクリアしていく必要があります。
しかし、退職を上司に伝える前にしっかりと下準備をしておけば、退職までの各ステップで発生しうる面倒を最小限に抑えられるでしょう。
中には悪質な引き留めを行うようなブラック企業があり、家に押しかけて退職を取り下げるまで帰らないと強硬手段に出る企業もあると聞きます。
退職や転職を検討中の方は、ここでご紹介したことを参考に円満退社への準備を進めてみてください。