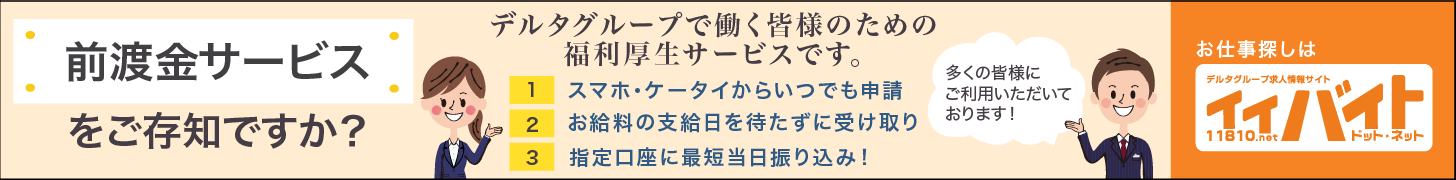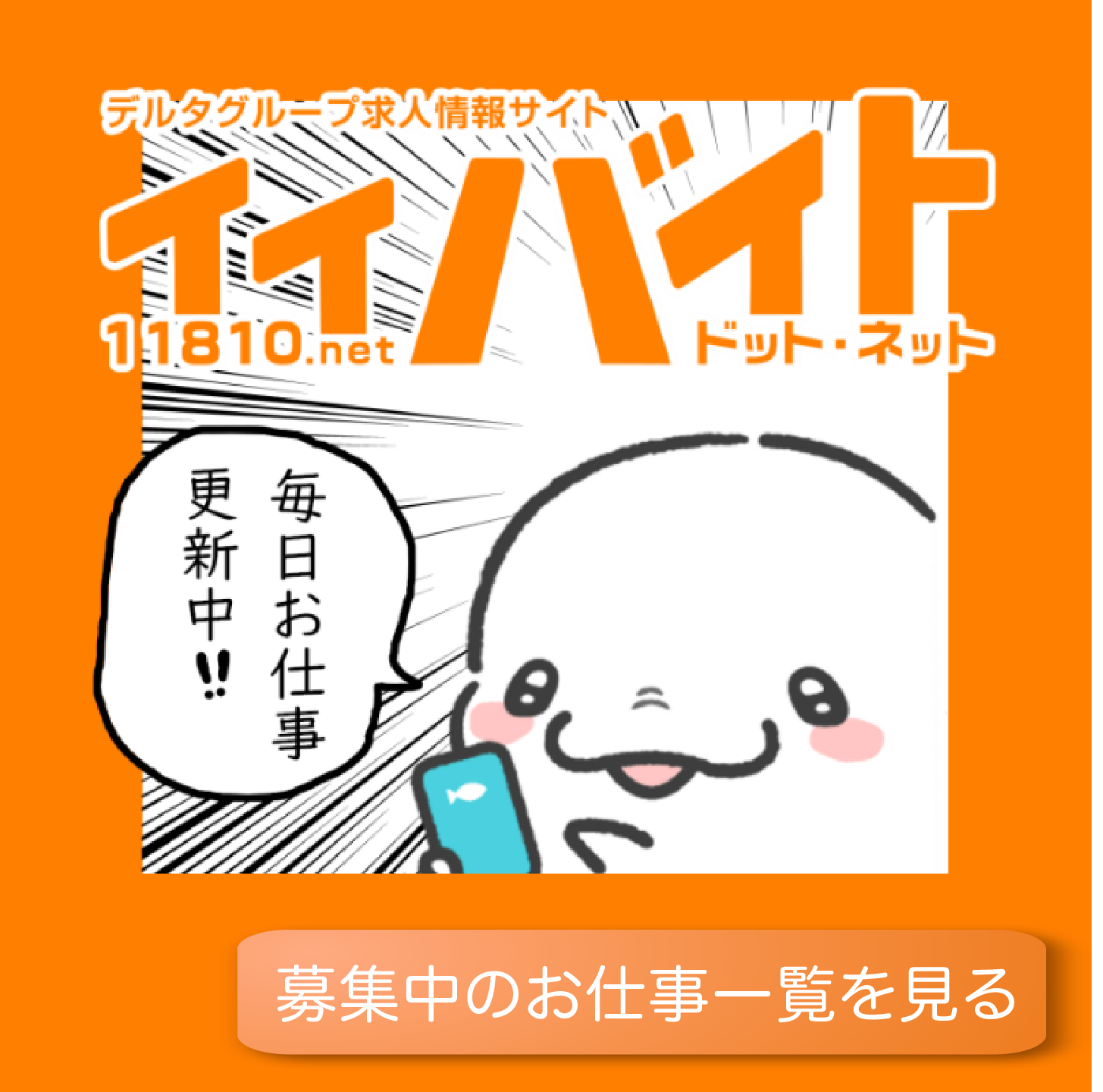禁止されている派遣なんてあるの!?
派遣にはいくつか禁止されている働き方があり、専ら派遣やグループ内派遣はその最たる例といえます。
これから派遣社員として働こうと考えているひとだけでなく、すでに派遣社員として働いているひとであっても、この2つのワードの意味を具体的にイメージするのは難しいのではないでしょうか。
この記事では専ら派遣とグループ内派遣の特徴に加えて、これら以外にも禁止されている派遣の働き方を解説します。
専ら派遣とは

専ら(もっぱら)派遣とは、派遣会社の派遣社員を特定の会社に限定して派遣することを指します。
派遣先が1社の場合はもちろんのこと、派遣先が複数であってもそれら以外に労働者を派遣していない場合には、専ら派遣とみなされ違法となります。
特定の会社にのみ人材を派遣するための派遣会社を作ってはいけないというものです。
後ほど紹介するグループ内派遣も、この専ら派遣と同じ性質を持つ違法行為です。
派遣会社の本質は、幅広い企業に対して労働者を派遣し、派遣先と派遣労働者双方のニーズに応えてることです。
専ら派遣はこの派遣会社の本分と反するため、労働者派遣法により禁止されているのです。
また専ら派遣がまかり通ってしまうと、企業は派遣社員ばかりを使用するようになり、正社員の雇用を奪う可能性もあります。
そのため専ら派遣には法律による規制が必要なのです。
専ら派遣と認定される条件には主に3つのパターンがあります。
それが下記3つです。
- 定款の事業目的に、専ら派遣であることが記載されていた場合
- 派遣先を広げるための営業活動や宣伝活動を行っていない場合
- 特定の派遣先以外からの派遣依頼を理由もなく断っていた場合
もっともわかりやすいのが、会社を運営していくための規則である定款の事業目的に、専ら派遣であることが記載されていた場合です。
また派遣先を広げるための営業活動や宣伝活動を行っていない場合や、特定の派遣先以外からの派遣依頼を理由もなく断っていた場合も、
特定企業以外との取引をする意思がないとして専ら派遣とみなされます。
ただしこの専ら派遣には例外的に認められるケースもあります。
具体的には、雇っている派遣労働者のなかで60歳以上の定年退職者の割合が3割以上に達している場合には、専ら派遣が認められるのです。
グループ内派遣とは

グループ内派遣とは、大手企業が小会社として派遣会社を設立し、その派遣会社から労働者派遣を受ける行為を指します。
小会社である派遣会社からの労働者派遣が、同じグループ内の企業全体に派遣されている労働者の8割を超えると、グループ内派遣とみなされ違法になります。
基準がやや曖昧である専ら派遣に、具体的な基準を設けたものがグループ内派遣と考えて差し支えありません。
要するにグループ内だけに人材を派遣するために派遣会社を立ち上げてはいけないという法律です。
グループ内派遣が労働者派遣法で禁止されている理由も、専ら派遣の禁止理由と同じく、派遣会社の本質から逸脱しているからとされています。
またグループ内派遣は、法律に則って雇用された派遣社員や正社員を雇うよりも、人件費を削減できるのが特徴です。
そのためグループ内派遣を許せば、専ら派遣のときと同様、企業はグループ内派遣からの派遣労働者ばかりを受け入れるようになり、正社員や法律に則った派遣社員の雇用を妨げることになりかねません。
そのためグループ内派遣は労働者派遣法により禁止されているのです。
他にも派遣には禁止されているものがある

労働者派遣法が禁止している働き方は、専ら派遣やグループ内派遣だけではありません。
労働者の権利を守るために様々な行為が禁止されています。
例えば派遣法では、一部の業務に対して労働者の派遣を禁じています。
具体的には、貨物船への荷物の積み降ろしや港湾倉庫における搬入出などの港湾運送業務、土木や建築などの建設業務、事務所や住宅などで行う警備業務、紹介予定派遣以外の医療関係業務、弁護士や司法書士などの士業が派遣を禁じられている業務です。
これらの業務に派遣が禁止されている理由には、業務それぞれに異なる理由があります。
たとえば建設業務の場合、労働者派遣を導入することで、雇用関係の明確化など建設労働者の雇用改善に悪影響を与えるためとされています。
また警備業務の場合、業務を適切に行うためには警備員を直接雇用し、指揮監督することが望ましいため、労働者の派遣が禁じられているのです。
労働者派遣法は、日雇い派遣と呼ばれる働き方も原則禁止としています。
日雇い派遣とは、
- 31日未満の派遣雇用契約
- 1週間に20時間の労働
どちらかに当てはまる派遣を指します。
日雇い派遣は派遣労働者が働きやすい環境を整えるのが難しいため、2012年から違法となりました。
しかし日雇い派遣の禁止にはいくつかの例外が認められています。
そのひとつが働くひとの性質によるものです。
60歳以上のひとや雇用保険の適用を受けない学生、年収500万円以上のひとなどは日雇い派遣で働くことが可能です。
また業務の内容によって日雇い派遣が認められているものもあります。
日雇い派遣が認められている業務には、ソフトウェア開発や財務処理、通訳や研究開発、金融商品の営業などがあります。
これらの業務は雇用が安定していて労働者保護の面からも問題がないため、例外的に日雇い派遣が認められているのです。
さらに派遣には「3年ルール」と呼ばれる派遣期間制限もあります。
派遣期間制限とは、同じ派遣社員が3年を超えて同じ派遣先で働くことや、同じ事業所が3年を超えて派遣労働者を受け入れることを禁止するものです。
前者を個人単位の期間制限と呼び、後者を事業所単位の期間制限と呼びます。
以前は業務によって制限の有無が決まっていましたが、2015年からは業務の区分がなくなりました。
専ら派遣やグループ内派遣など違法な派遣で働いていた場合

専ら派遣やグループ内派遣が発覚した場合、労働者派遣法違反となるため罰則が課せられます。
しかしあくまで罰則を受けるのは、派遣社員を使用していた経営者や企業であり、派遣労働者に罰則が課せられることはありません。
ただ罰則がないとはいえ雇用されていた派遣会社が倒産して無職になってしまうなど不都合が生じる可能性はあります。
なので、違法な派遣労働に悩んでいる場合には、なるべく早いうちに労働に関する相談を広く受け付けている公的機関に相談して違法な労働環境から逃れた方が良いでしょう。
相談窓口として一般的なのはハローワークです。
ハローワークと聞くと「仕事を探しに行くところ」というイメージが強いですが、労働に関する相談も受け付けています。
各都道府県のハローワークには、「労働者派遣事業適正運営協力員」という派遣労働者からの相談を専門に扱うスタッフがいるため、違法な派遣労働に関する専門的なアドバイスがもらえるのです。
また一般社団法人日本人材派遣協会も派遣社員からの相談を積極的に受け付けています。
この協会には、「労働者派遣事業アドバイザー」と呼ばれる専門スタッフがいるのが特徴です。
この他にも労働基準監督署や各都道府県に設置されている労働センターなどでも、違法な派遣労働に関する相談が可能です。
禁止されている働き方を知り安心して働こう

派遣という働き方には意外と知らない禁止事項が多く、知らず識らずトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
違法な働き方は派遣で働く人にとって不満や不安のもととなるため、できる限り避けるのが懸命です。
感情論を別にしても明日仕事を失ってしまうリスクも抱え込むことになりますし、何より法律を守らない企業は労働者へ正当な還元をしているのか疑問が残ります。
禁止されている派遣労働についての知識をインプットして、安心そして安全に派遣社員としてのキャリアを重ねましょう。