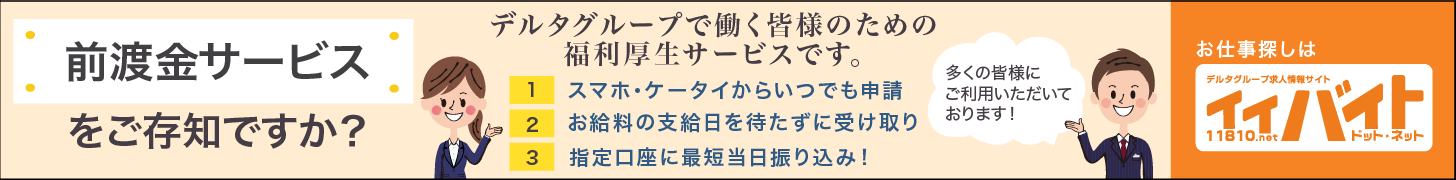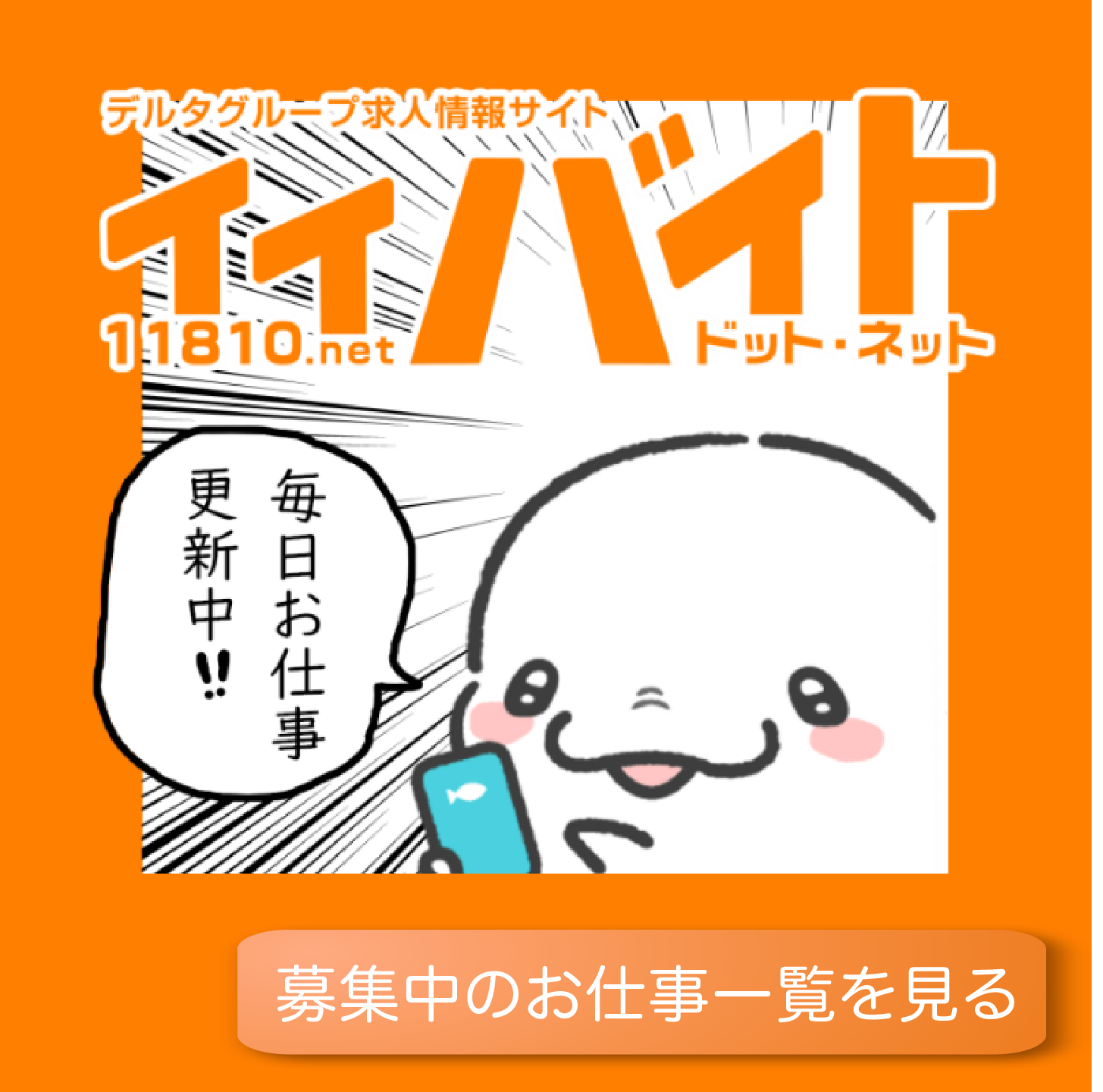「同一労働同一賃金」と言えば最近よく見かける言葉ですね。
もともとは英語の equal pay for equal work を翻訳した言葉です。
意味は読んで字の通り。
「同一の仕事に従事する労働者には、同一水準の賃金が支払われるべき」
ということです。
同一賃金同一労働とは?

これだけ読むと当たり前のことをなんでわざわざ言うのだろうと感じる人もいるかもしれません。でもこの言葉、結構奥が深いのです。
「国際労働機関(ILO)」ではこれを憲章の前文に挙げているほどです。
「世界人権宣言」においても「すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する」と規定されています。
「国際人権法」でも勤労権に関して『同一労働同一賃金』を明記しています。
ちょっと驚いてしまいますね。そこまで声高に主張されていることなのです。
具体的には性別、雇用形態(フルタイム、パートタイム、派遣社員など)、人種、宗教、国籍などに関係なく同一労働には同一水準の賃金をが支払われるべきということです。
逆に言えば、かつて人種や国籍や年齢や男女の違いによって、同じ仕事をしても明らかに支払われる賃金に差がありすぎる時期があったため、その反省に基づいて国際機関がそれを保障しようという動きになっているようなのです。
このうち、現在の日本において一番注目されているのは雇用形態による取り組みです。つまり、フルタイム、パートタイム、派遣社員など雇用形態が違っても同一水準にしましょうということですね。
当然、正規社員の収入を減らそうという取り組みにはならず、非正規社員の賃金水準を上げる方向になっていきます。だから、派遣などでの仕事探しにおいてはこれからチャンスが増えていくと考えられます。嬉しいことですね。
同一賃金同一労働で少子化問題にストップを

さて、国が前向きに同一労働同一賃金に取り組んでいる背景には労働者の平等のためにということだけではなくて現在の日本の特有の理由があります。
今、なぜ国は同一労働同一賃金をめざすのか?
安倍総理はこう語っています。
「(同一労働同一賃金にすれば)もう一度、中間層が厚みを増し、より多くの消費をするようになるでしょう。そうなれば、より多くの人が家族を持つようになるでしょう。そうなれば、日本の出生率は改善するのだと思います。」(平成28年9月21日ニューヨークでの金融・ビジネス関係者との対話における安倍総理講演)
つまり
→同一賃金同一労働にする
→非正規社員の賃金水準が上がる
→それによって個人消費が拡大する
→同時にそれによって個人が豊かになり出生率が上がる
→人口減少にストップをかける
→経済が成長する
なんとも壮大な構想ですね。
正規雇用でなくてもチャンスが

確かに現在の日本では全体の4割もの労働者が非正規雇用で働いており、待遇改善が進めばその人たちは豊かになりますし、さらに今まで働いていなかった女性や高齢者も仕事につきやすくなり、働き手不足の解消にもつながるとも言われています。以前ご紹介した「人手不足倒産」への対策にもなるでしょう。
「同一賃金同一労働」が話題になるときは、ある意味仕事探しにチャンスが増えているとも言えるわけです。注目していきたいものです。