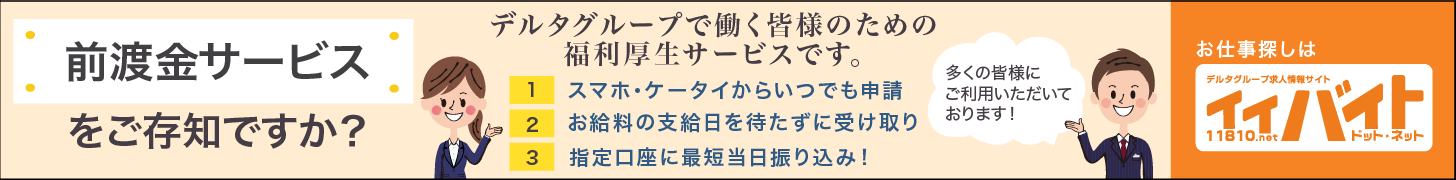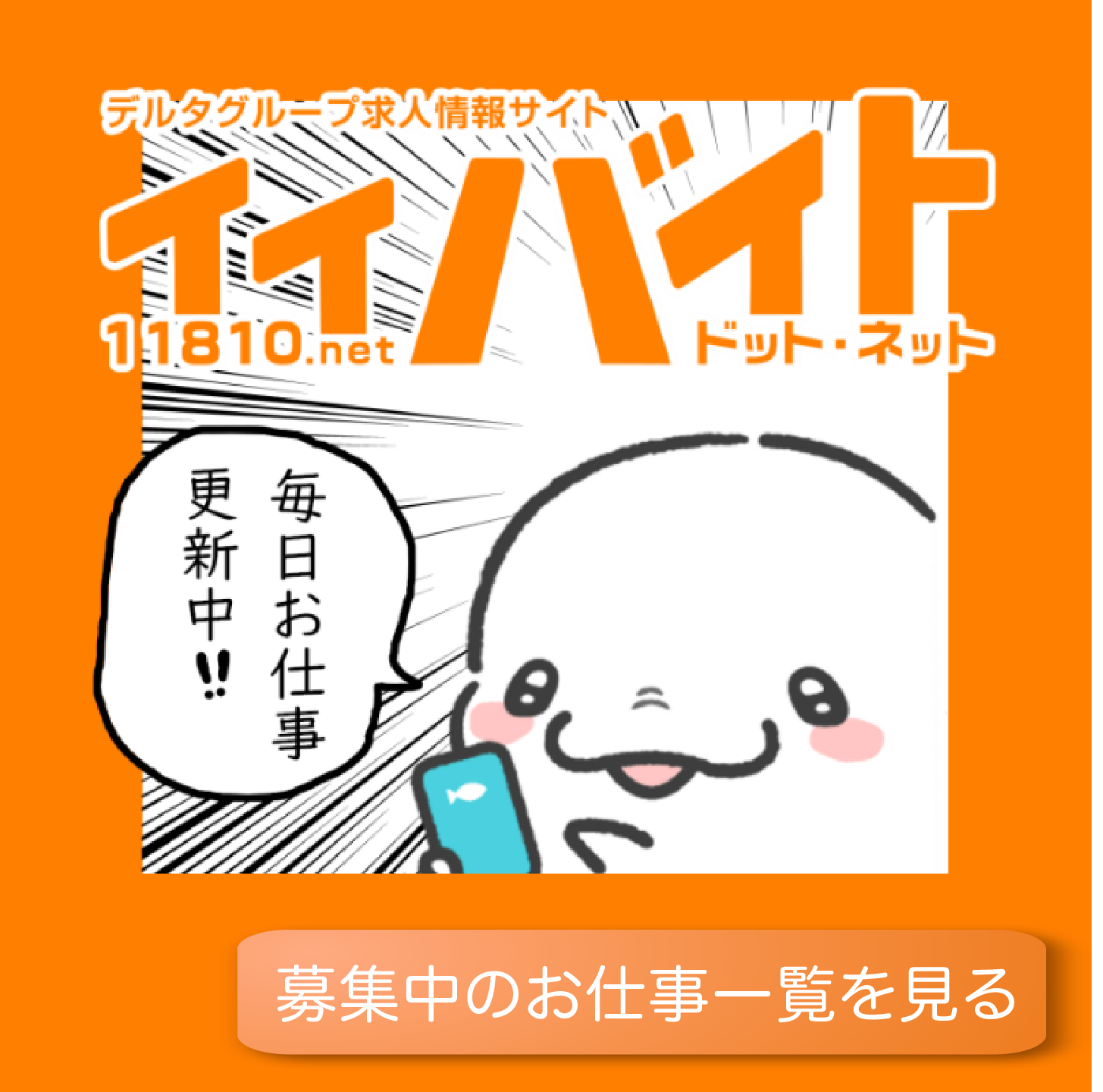「専門26業務」という言葉を耳にしたことはありますか。
人材派遣で働いた経験がある人の中には、聞いたことがある人もいるでしょう。
しかし、派遣に縁遠い人は聞いたことすらないと言う人の方が多いと思います。
いったいどんなものなのか、2015年に何があったのか、その後の影響はどうなっているのかなどを理解しておきましょう。
それに伴い、現在労働者派遣法がどのようになっているのかも理解しておくと、今後派遣社員として働くときに役に立ちます。
専門26業務とは

「担当する人のスキルや経験、センスによって仕事の完成度に大きな差が出てくる専門性の高い業務」のことを専門26業務といいます。
たとえば26業務の1つであるインテリアコーディネーターに新築の家のコーディネートを依頼した場合、依頼するコーディネーターが持つスキルや経験、センスや打ち合わせの内容をどのように受け取るかによって、完成するコーディネートは大きく異なるでしょう。
同じコーディネーターでも全く違う結果が出てくるように、完成する仕事の差が大きな仕事を「専門性の高い業務」と呼びます。
なお、専門26業務は前述のインテリアコーディネーターのほかに、放送業界で働く大道具や小道具、アナウンサーなどをはじめとして、秘書や翻訳、速記などビジネス関係、整備や事務用機器操作など、多岐にわたっています。
2012年10月に区分けが変更したため28業務となっていますが、26業務のほうが有名であるためここでは26業務のままです。
2015年に専門26業務は撤廃

通常の派遣社員が同じ会社で働ける期間は3年間でしたが、専門26業務はこの規定の対象外でした。
「3年ごとに違う人を雇用することによって、仕事のクオリティに大きな違いが出てしまうため、派遣期間を定めないようにすること」とされて専門26業務についている人は半永久的に同じ派遣先で働けました。
しかし2015年の派遣法の改正で、このルールは撤廃されました。
すべての業務で3年間の制限がつけられ、例外がほぼなくされています。
撤廃された理由
なぜ撤廃されたのか、その理由は大きく分けて下記の4つだと言われています。
- 専門26業務がほかの業務と比べて専門性が高いと言えない
- 「職種によって雇える期間が異なる制度」がわかりにくかった
- 制限がないため半永久的に派遣社員を雇える
- 悪質な派遣会社が多く登場するようになった
1〜3に関しては文字通りに理由ですが、4の悪質な派遣会社が多く登場するようになったからと言う理由には

と思われた人もいるかもしれません。
実はそれまで派遣会社には特定派遣と一般派遣が存在していました。
特定派遣は派遣会社の契約社員として派遣先で働くこと、一般派遣は派遣会社に登録し、派遣先が決まってから派遣会社と働く人が契約する現在の派遣会社のやり方です。
一般派遣は厚生労働大臣に許可を取らなければなりませんでしたが、特定派遣だけなら届け出だけでできました。
その結果、専門26業務に当てはまらない一般事務でも無理やり専門26業務に該当するとみなし、不当に派遣社員を雇用する企業や派遣会社が多くなりました。
いつでも首を切れる社員を雇用する会社と、提供する派遣会社が増えたことになります。
派遣社員側は、一見無期限に雇ってもらえるからよさそうと思われがちですが、安定性や保証はないため却ってデメリットが多かったのが実情です。
26業務撤廃での影響

撤廃での影響として、専門26業務を取り扱ってきた特定派遣というカテゴリがなくなり、すべての派遣会社は厚生労働大臣に許可を取ることが必須となっています。
雇用形態としては個人単位や事業単位といった上限ができました。
個人単位は同じ事業所に3年以上派遣できないというルールです。
例えばある会社の営業で働いていた人が、3年後は別の会社の営業で働いても、今まで働いていた会社の総務で働いても良いことになっています。
3年の上限に達したら派遣会社が雇用していた会社に直接雇用してもらうよう頼むことや、新しい働き先の情報提供など、雇われていた人が安定して働けるようにしなければならなくなりました。
事業所単位は派遣先の事業所が、3年間以上派遣社員を利用してはいけないルールとなっています。
ある会社の九州支社で3年間派遣社員を利用したら、派遣先の過半数労働組合が許可した場合など例外を除きその後九州支社には社員を派遣することができません。
この場合、九州支社にいた派遣社員は、北海道支社や東北支社では働けるのが特徴です。
ただし、このルールにも例外はあり、先ほども少し書きましたが、派遣先の過半数労働組合が許可した場合は3年以上働くことができるようになります。
また派遣先の過半数労働組合が許可していなくてもこの3年ルールに当てはまらない人もおりそれが60歳以上の人や、派遣会社に無期雇用されている人、産前・産後休業の人の代わりの業務をしている人などと例外的な扱いとなっています。
撤廃によるメリット・デメリット
一番大きなメリットは3年以降継続して働くためには派遣元で無期雇用社員になるか派遣先が労働者を直接雇用しなくてはいけなくなり、派遣先と労働者双方が望んだ場合はより安定した雇用がなされると言うことです
また、自由な働き方ができるようになったため、自分のスキルアップや成長によって仕事を選べるようになりました。
デメリットは、3年以内の契約期間であればいいと、派遣先の会社側が2年10か月や2年11か月の契約期間で派遣社員を募集することです。
2年10か月であれば3年ルールに縛られることなく、延長なしで契約終了させることができます。
結果として、企業に都合の良い派遣社員だけが働いている会社も少なくありません。
近年の労働者派遣法の改正

さて、派遣という働き方ができてから長い時代が過ぎ社会のあり方も変化してきました。
その変化に対応し労働者を守るべく、26業務撤廃以外にもいくつかの法改正が行われてきました。
ここではそのうちの代表例を2つご紹介します。
日雇い派遣の原則廃止
2012年に労働者派遣法が改正され、原則日雇い派遣は禁止となりました。
派遣社員として働く場合、派遣期間が最低でも31日以上必要です。
理由として、派遣切り、ワーキングプアなどの問題が増加したからです。
ただし、デモンストレーションやソフトウェア開発など例外となる業務や、60歳以上や雇用保険の適用外である学生など、特定の条件に当てはまる人は日雇い派遣で働けます。
また、日々紹介と呼ばれる単発の日雇い紹介業務は、派遣ではないため対象外となっています。。
同一労働同一賃金
労働者派遣法ではなく「働き方改革関連法」改正によって、2019年4月から施行されました。
しかし、派遣社員と大きく関係がある制度となっています。
2020年4月より、大企業で一斉に施行された制度です。
中小企業では2021年4月から施行されます。
企業は派遣社員と派遣先で働く従業員との待遇格差を改善しなければなりません。
派遣社員を受け入れる場合、企業は給料の見直しだけでなく通勤手当の支給や食堂・休憩室などの使用ルールなどの検討が必要です。
理由の一つに、派遣社員の待遇差別がありました。
社員は社員食堂を使用可能で、派遣社員は使用不可能といったことをはじめ、賃金や待遇面での差別化を改選するための制度です。
派遣社員を不当な雇用から守るための撤廃

専門26業務が撤廃されたのは、企業に都合の良い働き方から、派遣社員を守るためといえます。
派遣社員が正規雇用してもらいやすくなったことや、自分のスキルを高めるために働けるようになりました。
3年近く務めた派遣先で安定した雇用を望むなら派遣元と派遣先に掛け合い無期雇用や直接雇用に契約を切り替えるなどの交渉してみても良いかもしれません。
専門26業務の撤廃以外にも同一労働同一賃金など昔と比べ派遣社員に有利な制度が整ってきました。
転職する際はぜひ派遣社員も選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか?