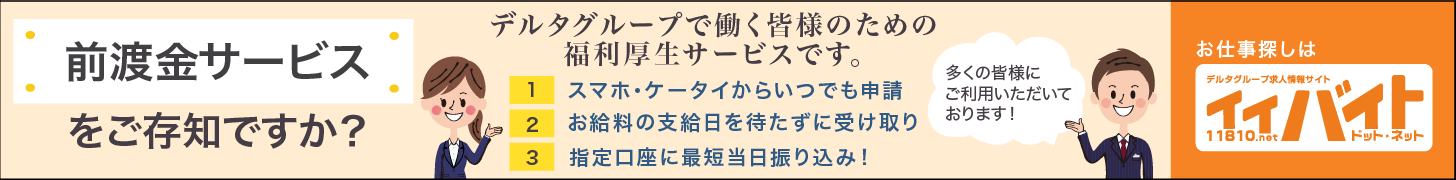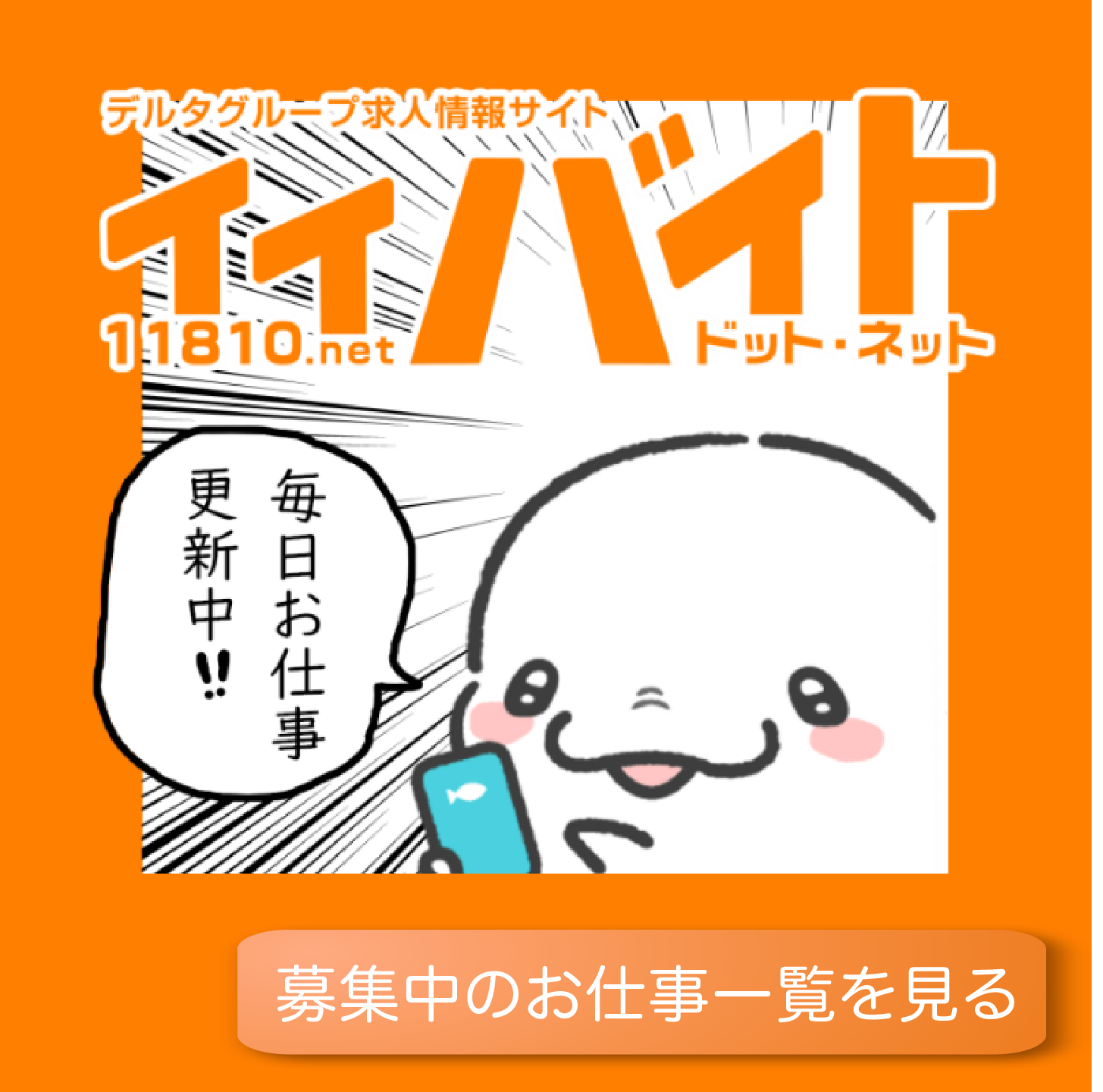うちの職場大丈夫かな???
働き方の一つとしてアルバイトを選択している人も少なくないでしょう。
しっかりと認められた働く方法の一つではありますが、その手軽さゆえ、アルバイトで働く人への福利厚生が軽視されがちなことが多いです。
アルバイトといえ、労働基準法は適用されますし、ある程度以上の収入があれば税金や社会保険についても考慮しなければなりません。
権利と義務をしっかり理解することが重要です。
この記事ではアルバイトの有給や税金、社会保険などについて解説していきます。
アルバイトも社会人!色々な法律やマナーがある

アルバイトでも労働基準法は適用されるので有給は取得できますし、残業代も支払われます。
一定の時間以上働けば、休憩に入らなければなりません。
また、ある程度以上の収入があれば、社会保険料や税金についても考慮する必要があります。
簡単に始められて簡単に辞められるイメージがあるかもしれませんが、アルバイトといえど義務と権利は発生します。
アルバイト先から不当な扱いを受けたりすることのないよう、労働基準法や税金についてしっかり理解したうえでアルバイトとして働くようにした方がよいでしょう。
ですが、アルバイトも社会人です。
権利ばかりを主張してはいられません。
働く上での決まり事やマナーは当然あります。
無断欠席をしない、遅刻をしないなどの最低限のマナーはもちろんですが、守秘義務などの法律上順守しなければならない義務が発生することもあるでしょう。
職種によって守らなくてはならないことは異なります。
会社の考えや、上司に従ってその職種に沿った働き方をすることが重要です。
アルバイトも労働基準法に守られている!有給も残業代もでる!

権利ばかり主張していられないと書きましたがとはいえ大前提としてアルバイトだからと言って法律に反した働き方はできません。
アルバイトにも労働基準法は適用されますし法律を遵守している働き方をしているということが前提です。
6時間を超えて働く場合には勤務時間に合わせた休憩時間が必要ですし、仕事中だけではなく、準備や後片付けなどの時間分もアルバイト代として請求できます。
また、法律上1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と定められているため、これを超過した場合、決められた残業代が支払われなくてはなりません。
有給に関しても認識は同じで、アルバイトにも適用されます。
雇用開始から6ヶ月以上継続勤務し、決められた労働日数の8割以上出勤していれば、有給を取得することが可能です。
法律で定めているルールはあくまで最低ラインを定めているものなので良い会社の場合はこれよりも緩いルールで有給を支給してくれる会社もあります。
有給を申請するときの都合は本人都合でよく、どのような用途で有給を申請しても会社側に咎めることはできません。
正社員であろうが、アルバイトであろうが適用されます。
ほかにも、給与に関してのトラブルが多いので注意が必要です。
給与の未払いや研修期間という名目での給与の減額、ペナルティとしての減給など、多くの事例がありますが、労働基準法に違反しているケースも少なくありません。
アルバイト先と何らかのトラブルが起きてしまった場合、最寄りの労働基準監督署に相談するようにしてください。
アルバイトでも正社員でも働く側の権利は保障されなければなりません。
アルバイトだからこれらのことが許されるなどということはあってはならないことです。
アルバイトでも労働基準法に守られているということを覚えて働くようにしてください。
税金や社会保険についても考えよう
アルバイトにも労働基準法が適用されますが、収入によっては
- 社会保険料
- 所得税
- 住民税
といった保険や税金関係のことも発生します。
まずは所得税についてです。
所得に応じてかかる税金を所得税と言います。
所得税には控除というシステムがあり、誰でも受けられる基礎控除が38万円、給与所得控除が65万円となっているので、合計103万円までは税金がかかりません。
このラインを超えると、アルバイトでも所得税が発生します。
住民税は取得税とは異なる計算方法で計算され、市区町村ごとに異なり、少し複雑ですが、大まかな目安としては100万円まで住民税はかからないでしょう。
ですが、所得税のかからない年収103万円でも、住民税は負担しなくてはならないので注意が必要です。
学校に通いながらアルバイトをしている人も多いでしょう。
学生さんは、上記の所得控除に加えて、勤労学生控除を申請すれば更に27万円の控除額を上乗せさせることができます。
つまり、103万円に27万円を足して130万円まで所得税がかかりません。
ですが、親御さんなど世帯主の扶養に入っていると、年収103万円を超えると世帯主が納める税金が増えてしまいますので、気を付けましょう。
複数のアルバイトを掛け持っている人は総額の年収で税金が決まってくるので、その辺りもしっかり押さえておく必要があります。
稼ぎすぎてしまって却って損をしてしまうことのないように注意しましょう。
また、アルバイトでも確定申告を行った方がよいケースもあります。
払いすぎてしまった税金を取り戻すチャンスなので、該当する場合は面倒くさがらずに、確定申告を行いましょう。
これらのように、アルバイトでも、所得によって税金や社会保険を考えなくてはならないことがあります。何も知らなかった、では損をしてしまうことがあるので、これらのことについても、理解しておいた方がよいでしょう。
アルバイトでも社会人として最低限のマナーを

最後に、いくらアルバイトとはいえ、最低限のマナーは必要です。
無断欠勤をしない、遅刻をしない、言葉遣いはきちんとする、社会人としての常識を持って働くことが大切です。
最低限のマナーも守らず、自分の権利だけを主張してはいけません。
気を遣いすぎることはありませんが、自分からトラブルの火種になりそうなことはしない、というのは鉄則です。
自分も相手も働きやすいように心掛けて過ごすことが重要です。
ですが、バイト先の中にはブラックなバイト先もあるでしょう。
そのような所でずっと働き続けることはありません。
不当なノルマ、欠勤に対する罰金、希望休が通らない、意図しないシフトが入っている、セクハラパワハラ、様々なことが起こる可能性がありますが、何も我慢する必要はありません。
働く側にも権利はありますし、辞めてしまうのも一つの手です。
ですが、自分だけではどうしたらよいのかわからない人もいるでしょう。
そのようなときは迷うことなくしかるべき機関に相談するようにしてください。
専門の人が話を聞いてくれますので、正しい対処の仕方がわかります。
アルバイトとして働くときに

アルバイトでも労働基準法に守られていますし、税金関連の知識も必要になってきます。
正社員じゃないから、といっておろそかにしていると損をしてしまうこともあるので、身に着けられる知識は身に着けておいた方がよいでしょう。
また、自分ではどうしようもなくなったり、どうしたらよいのか迷ってしまったときには、一人で悩まず、周囲に相談するようにしましょう。
アルバイトが不安なら派遣という働き方
ここまでアルバイトについて法律面を中心にご紹介してきましたが、中にはアルバイトで働くことを不安に感じた人もいることでしょう。
特に個人経営店でアルバイトをする場合、こういった労務管理に手が回っていない店舗も多く違法な労働を指示されることもあると思います。
もし、そういったリスクが怖い人は派遣会社で働くという選択肢をお勧めします。
派遣会社は人材業界のプロです。
常に1000人単位で派遣社員を雇用している会社も少なくありません。
こういった雇用人数の多い企業は労働基準法違反や労務管理のミスが非常に大きな問題となるリスクがありためしっかりとした管理が行われているので労働者にとっては安心感があります。
派遣の求人案件にもアルバイトと同じ短時間労働をメインターゲットにした物も多くあり、学生や主婦が収入を得るという目的は問題なく達成できることでしょう。
もしこの記事を読んでアルバイトだけでなく派遣社員の求人にも興味を持っていただけたのなら是非一度弊社に登録してみてはいかがでしょうか?
弊社コーディネーターがあなたに最適な求人をご提案させていただきます。